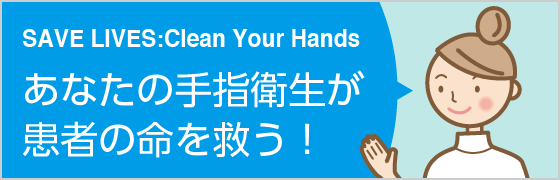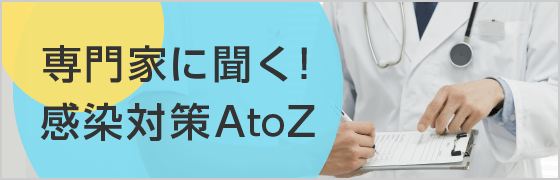製品導入事例
起立補助器の導入で、職員の腰痛軽減だけでなく、患者の離床意欲が向上!
- 愛媛医療生活協同組合 愛媛生協病院
-

住所 〒791-1102
愛媛県松山市来住町1091-1病床数 88床
(急性期病棟:44床、地域包括ケア病棟:44床)全職員数 280名(2024年9月現在) 手術件数 472件/年(2023年1~12月) 病院ホームページ https://www.e-seikyo-hp.jp/index.php ※上記のリンク先ウェブサイトはサラヤ株式会社の個人情報保護方針は適用されません。
リンク先の個人情報保護方針をご確認ください。愛媛生協病院は「患者さんの立場に立って親切で良い医療」「いつでも、どこでも、安心して医療が受けられること」を目指して、1986年4月に開設しました。
松山市の二次救急輪番病院として急性期医療を提供しつつ、介護分野においては23床のショートステイ施設を運営し、医療と介護の連携を図っています。
超高齢社会を見据えた地域包括ケアシステムにおいて、リハビリ機能を強化した「地域包括ケア病棟」を有した「機能強化型在宅支援病院」として在宅医療機能を充実させ、松山市東南部の医療施設や介護事業所と連携し、病気になっても住み慣れた地域で生活を続けられるよう支援しています。
- 導入製品
-
-

起立補助器
製品情報はこちら
Sara® Stedy Compact
-
※Sara®はarjoグループの登録商標です。
使用対象:歩行補助機器、または人的介助がなければ歩行が難しい方。
端座位での保持が見守りで可能、かつ臀部を座面から浮かせられる方。
はじめに
当院では、Sara® Stedy Compactをはじめに地域包括ケア病棟に1台導入し、その後急性期病棟にも1台導入して運用しています。先に導入した地域包括ケア病棟は、20~50代と幅広い年齢層の職員が勤務しており、看護師26名、介護士8名、看護助手3名、補助事務2名、合計39名で構成されています。地域包括ケア病棟では、体重が車椅子の耐荷重を上回る患者さんを対象に、Sara® Stedy Compactを活用しています。
入院患者さんの病状に応じて状況は異なりますが、このような患者さんが同時期に入院することが少ないため、通常Sara® Stedy Compactは、最大で2名の患者さんに使用しています。Sara® Stedy Compactの導入により、体格の大きい患者さんのトイレ介助等が容易になり、離床の促進にも寄与しています。
起立補助器 Sara® Stedy Compact 初導入までの道のり
- 起立補助器の導入を検討された背景は?
当院では安全衛生委員会が、毎年腰痛調査をしており、直近の結果では約半数の職員が腰痛を有していました。さらに地域包括ケア病棟の職員は、39名中26名が腰痛の経験があります(有訴率:約66%)。
今後、労働人口の減少や職員の高齢化が進行するなかで、患者さんを抱え上げることによる腰や膝などの故障が、離職の要因となる可能性があるため、“抱え上げない介助(ノーリフティングケア)”の導入が必要と考えていました。
一方で、ケアの観点では、体重が100kgに近い患者さんの移乗介助に課題を抱えていました。このような大柄な患者さんに対しては、職員2~3名での移乗介助を行っていましたが、移乗することに必死になるあまり、車椅子のフットレストなどに患者さんの皮ふが擦れてしまうことで、表皮剥離や内出血等のスキン-テアが発生することがありました。また、離床や日常生活動作の再獲得に向けた支援が不十分であることに課題を感じており、職員と患者さんの双方がより楽に安全に移乗できる方法について常に模索していました。
そのような状況のなかで、他法人の連携病院に見学へ行く機会があり、これらの課題を解決できる起立補助器としてSara® Stedy Compactをご紹介いただきました。
- Sara® Stedy Compact 導入の決め手は何でしたか?
使用対象者の選定が容易で、操作がシンプルな点です。連携病院へ訪問した際に、様々なリフトを拝見しましたが、なかでも Sara® Stedy Compactはトイレ移乗が簡単にできることに魅力を感じました。患者さんは Sara® Stedy Compactへ移乗した後、そのままトイレへ移動し、便座の近くまで接近することができます。さらに、患者さんに腰を下ろしていただくだけで便座への移乗が可能です。排泄後は患者さんに腰を上げていただき、再度 Sara® Stedy Compactへ移乗いただきます。このように、患者さん自身で起立保持ができれば使用できるため、対象者の選定を迷わせない点も魅力的でした。
デモンストレーション期間中に、当院で最初に使用した患者さんが外の景色を見て、「こりゃ、えぇわい」と笑顔でおっしゃったことは、非常に印象的でした。車椅子だと座面が低く、普段は窓から景色を眺める機会が少ないですが、 Sara® Stedy Compactは車椅子よりも座面が高いので、自然と視点が高くなります。さらに視点が高くなることで、立っているように感じることができ、患者さんのリハビリに対する意欲が高まります。その結果、離床への意欲も向上すると考えます。
このように、 Sara® Stedy Compactを導入することで、トイレ介助や移動の手段にとどまらず、患者さんの生活の質が向上することを実感しました。


- 導入前に不安なことはありましたか?
特に不安なことはありませんでしたが、導入に際してはまず賛同してくれる仲間を集めることが重要と考えました。そこで、連携病院へ一緒に見学へ行った当院の看護師長と思案し、院内キャンペーンを実施しました。具体的には、デモンストレーション期間中に、できるだけ多くの職員が Sara® Stedy Compactに触れる機会を設け、優れた性能を体感してもらいました。また、当時の事務長にも試乗してもらい、コンパクトで軽量、かつ安全性を担保できていることを訴求した結果、購入を検討することになりました。
起立補助器 Sara® Stedy Compact の導入後
- 地域包括ケア病棟で Sara® Stedy Compactはどのように運用されていますか?
現在は多いときで2名の患者さんに使用しています。おもに排泄介助の移乗(ベッド↔トイレの便座)と、入浴介助時の移動(ベッド↔脱衣所)に使用しています。当院ではSara® Stedy Compactのキャスターがベッドの脚と干渉しますが、患者さんに足を少し前に出していただくことで、問題なく使用できています。さらにSara® Stedy Compactへの移乗時には、座位を安定させるために膝を膝パッドにしっかりと当てていただくように介助者が声をかけることを心掛けています。

対象者の選定は、看護師と介護士が日々のケアの中で協議しながら進めています。毎月行われる看護補助者部会において、Sara® Stedy Compactの使用状況や患者さんの状態を確認し、対象者の拡大を目指してディスカッションを行っています。なかには、臀部を上げることができず1回で移乗できない患者さんもいますが、何度も挑戦することがリハビリとなり、歩行訓練にもつながると考えます。
Sara® Stedy Compactの使用後は、患者さんが握ったハンドル部分や、座面シートをサラサイド除菌クロス(製造販売:サラヤ株式会社)で清拭して感染対策にも心掛けています。
地域包括ケア病棟において、Sara® Stedy Compactは普段廊下に保管しており、必要に応じてそこから取り出して使用し、使用後は元の場所に戻すことを徹底しています。


(地域包括ケア病棟)
-Sara® Stedy Compact を導入してよかったと感じる点は?
職員・患者さん双方に安心感と自信が生まれました。導入前は体重が100kg近い大柄な患者さんに対して、職員が力負けしていました。Sara® Stedy Compactの導入後は力負けすることなく移乗介助が可能になったことから、積極的に離床をすすめることで、患者さんのリハビリがスムーズに進むようになりました。その結果として、Sara® Stedy Compactを使用しなくてもよい状態まで回復する期間が早まったように感じます。つい先日までSara® Stedy Compactを利用していた患者さんが、廊下でのリハビリ中に車椅子から立ち上がる姿を見て、軽介助でのリハビリが可能になったことに大変驚いたこともありました。
-導入後の評判はいかがですか?
利便性が高く、現場で重宝しています。約5年前に、当院の通所リハビリテーション(デイケア)では、他のリフトを導入しましたが、ほとんど使用されることなく倉庫に保管されていました。そのリフトは、当時膝の拘縮などにより起立が困難な方や、まっすぐ立つことができない方に使用されていましたが、対象者が限られており、1人の患者さんにしか使用されていませんでした。それに対して、Sara® Stedy Compactは対象者が広く、手軽に使用できるため、導入後も継続して活用しています。
また患者さんの負担も軽減されています。以前はトイレでの排泄に消極的だった患者さんが、「これでやったら、トイレに行ってもいいよ」と言ってくれるようになりました。トイレの便座に移る際、車椅子から立ち上がり、回転して座るという一連の動作に対して、患者さんは負担を感じていましたが、この動作が不要になったことで、負担が軽減されました。さらに、プライバシーが確保されたトイレ空間で、患者さん1人で排泄できるようになったことで、表情が明るくなったように感じます。このことからも、人間としての基本的な行為が適切に行えることは非常に重要で、自立支援につながると感じました。
-急性期病棟ではどのように活用されていますか?
急性期病棟の患者さんは、術後疼痛や人工呼吸器・点滴・ドレーン等で身体の動きが制限され、介助者の支援が必要な方が多いのが特徴です。このような患者さんは日常生活動作を取り戻していくことが、闘病意欲を高め、回復を早める重要な要素となります。この観点から、急性期ではSara® Stedy Compactを活用した日常生活の支援が非常に重要であると考えています。
NEXT STEP
- 今後どのような取り組みをしていきたいですか?
ノーリフティングケアを文化として根付かせたいです。約2年前に法人内の看護委員会で小規模に始まった取り組みですが、当院では病院全体でノーリフティングケアに取り組むことを院長名で宣言し、2024年から院内全体で取り組みを開始したところです。当初は看護師と介護士のみでの実施を予定していましたが、安全衛生委員会を主軸に、セラピストをはじめ各部署の職責者を巻き込み、看護師・介護士はリンクスタッフを育成しながら進めています。しかし、ノーリフティングケアの概念が、十分に浸透していないことが現状の課題であるため、全職員を対象に研修予定です。座学だけではケア技術の習得は難しいため、実技と講義を組み合わせて実施し、職員自身の腰痛の原因を理解できるような仕組みを構築していくのが目標です。さらに介助が難しい患者さんがいる場合には、「どのように対応すればよいか」と相談ができる環境づくりを目指しています。
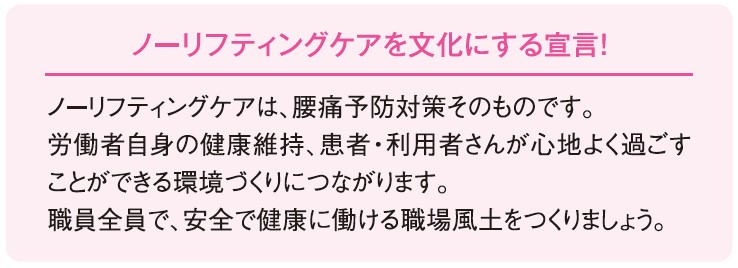
加えて、Sara® Stedy Compactの活用の幅を広げていきたいと考えています。今後、Sara® Stedy Compactの対象者を増やすなかで、全職員が安全に対応できるように、対象者の可視化が必要と考えます。具体的には、マニュアルの作成や、患者さんの自立度を判別できるように(車椅子を使用しているのか、見守りのもとで歩行器を使用しているのか、Sara® Stedy Compactを使用しているのか)ピクトグラムで示していきたいです。
- ノーリフティングケアに対する考えをお聞かせください
ノーリフティングケアは、職員の負担を軽減するだけでなく、患者さんの生きる力や意欲を引き出すための重要な取り組みであると認識しています。さらに患者さんのポジティブな変化が職員の働きがいを向上させ、腰痛予防にも寄与することで職員の定着にもつながるという観点からも、今後医療・介護ニーズが高まっていくなかで特に重要な取り組みであると考えています。

- 今回インタビューさせていただいた方
-
-

新田 智加 様
介護福祉士
-

森実 美佐 様
総看護師長
-

大西 壽美子 様
前:事務長、現:専務理事
-
- 編集後記
-
今回の取材を通して、Sara® Stedy Compactの導入により職員・患者さん双方の身体的負担軽減だけでなく、患者さんの離床意欲・QOLが向上したことに喜びを感じました。今後とも“ノーリフティングケア”に、Sara® Stedy Compactをお役立ていただけるよう、“ノーリフティングケア”の導入をご検討中の方や、介助支援機器にご関心をお寄せいただいている方々へ有益なご提案をできるように精進してまいります。(サラヤ株式会社 学術部)
取材日:2024年9月4日
電話によるお問合せ:06-4706-3938(受付時間:平日9:00~18:00)